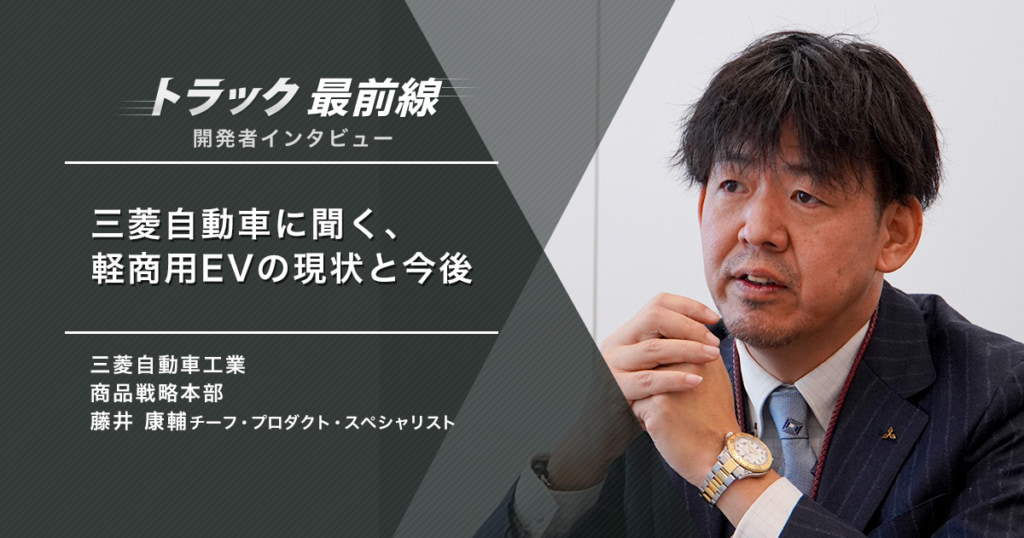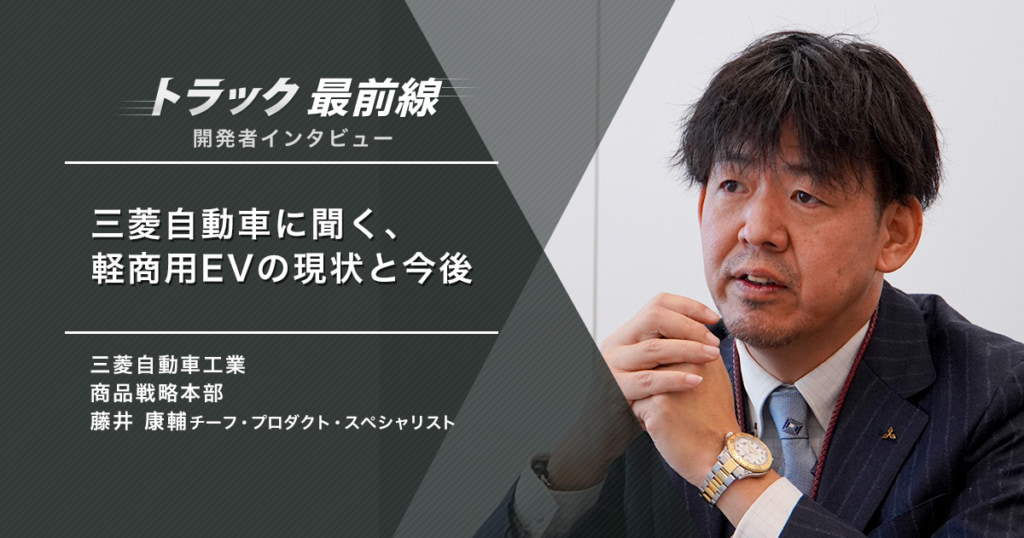
三菱自動車工業は昨年末、新型軽商用EV「ミニキャブEV」を発売した。2011年の登場以来、12年間で約1万3000台を販売した軽商用EV「ミニキャブ・ミーブ」をベースにしながらも、大幅な改良で最新商用EVに相応しい実力を備えている。物流業界全体でカーボンニュートラル達成に向けた取り組みが進められる中、軽商用車のEV化も大きなカギを握るが、その中で三菱自動車は軽商用EV市場をどのように捉え、取り組んでいるか、三菱自動車工業 商品戦略本部藤井康輔チーフ・プロダクト・スペシャリストにお聞きした。(取材日:12月26日)
<三菱自動車が23年末に発売した軽商用EV「ミニキャブEV」>

燃料代の高騰がEV導入を後押し
―― 最近は小型トラックでもEVの導入が始まり、物流業界全体でEVへの注目度が増しているように見えます。一方でラストワンマイルの主役である、軽商用車ユーザーの動向はいかがでしょうか。
藤井 基本的には軽商用バンで重視されている大きなポイントは、それほど変わっていないと思います。荷室の使い勝手や取り回し、車両価格など、基本的なポイントというのは何十年も変わっていない。
ただ、最近の特徴として、安全性を重視しているオーナーさんが増えてきています。先進的な安全装備、衝突被害軽減ブレーキや誤発進防止機能など、ドライバーの安全や事故を防ぐ装備を重視されている方が増えてきているというのが、最近の傾向ですね。
一方で、社会全体が環境重視になり、政府のカーボンニュートラルへの動きなどもあって、かなり前から軽商用EV自体への興味は多くの方が持たれています。ウチはまったくEVを導入する気ありません、という企業は、ほとんど無いに等しいぐらい意識としてはあります。でも、実際導入するかとなると、価格が高い、充電インフラが整っていない、航続距離が短い、といったところが障壁になって、なかなか実際に導入までには至らなかった企業が多かった。
しかし、環境への意識が非常に高まってきていることに加えて、燃料代が高騰したことで、トータルのランニングコストを考えるとEVのメリットが大きくなっています。そこでEV導入を検討する企業が増えてきたのも最近の傾向です。
今、仮に月に1500キロ走行するパターンで7年間乗ると、電気代はガソリン代の約70%で済む計算になります。燃料代以外も含めたトータルで考えると、走行距離にもよりますが、7年ぐらい乗られると十分メリットを享受できる感じです。
―― コスト面での障壁がなくなってきたということですね。
藤井 今まではどちらかというと、自社の環境アピールみたいな面が大きかったと思います。それが、本当の実用性やコストなども考えて、EVをそろそろ入れてもいいんじゃないか。「将来」と言っていたのが徐々に「今」かな、というふうに動き始めているように思います。
<三菱自動車工業 商品戦略本部 藤井康輔チーフ・プロダクト・スペシャリスト>

―― EVを本格的に導入する条件が、ようやく整ってきたタイミングといえそうですね。ただ、充電インフラの整備が追い付いていない感もあります。
藤井 特に都内などでは、狭い場所にある営業所なども多く、自社の敷地内に充電器を設置するのも簡単ではありません。複数台のEVを一つの拠点に配備するならなおさらです。
そういったところもEV導入の障壁になっていますね。「じゃどうしているんですか?」と言うと、休憩時間やルート途中で急速充電しています、という方もいらっしゃいます。
―― 公共の充電スポットですか。
藤井 そうですね。あとは三菱や日産のディーラーとか、充電器を設置しているコンビニで入れている、という方もいらっしゃいます。
ですが、ほとんどのお客様は、充電を夜にして、朝、満充電で乗って行くという使い方をしています。距離を走る方は、昼休みに店舗に戻って来た時に継ぎ足し充電して、また出ていかれるという方が多いです。なので充電器がきちんと確保できないところは、なかなか難しいのが実情です。
―― その辺はこれから社会全体の課題ですね。
藤井 そうですね。しかし、政府のカーボンニュートラル施策として、充電器を拡充する計画にはなっているので、予定通り進めば使い方も幅が広がってくると考えています。
軽商用EVユーザーの要望に応える新型「ミニキャブEV」
―― 三菱自動車は、2011年から軽商用EVのミニキャブ・ミーブを販売されてきました。軽商用EVの販売について、10年以上の蓄積があるわけですが、ミニキャブ・ミーブのユーザーからは、どのような要望や評価が多かったのですか。
藤井 安全性能を強化して欲しいということ、それから航続距離をもう少し伸ばして欲しいという声が多かったです。
ミニキャブ・ミーブの航続距離は133kmでした。我々が持っているデータでは、軽バンのお客様の80%は1日の走行距離が90km以下なので、スペック上は大部分のお客様をカバーできることになる。でも、実際には不安を感じるお客様も少なくない。また、拠点の充電器が少なくて、昼休みの継ぎ足し充電が間に合わないという方もいらっしゃいました。そのようなことを考えると、航続距離にもう少し余裕が欲しいという声が多かったです。
―― 新型のミニキャブEVでは、そこが大きな改善ポイントになったわけですね。
藤井 まず安全性能では、衝突被害軽減ブレーキシステムや車線逸脱警報システム、オートマチックハイビーム、誤発進抑制機能(前進時)などの予防安全技術「三菱e-Assist」を採用し、サポカーSワイドに対応しました。
航続距離については、電池容量の拡大とモーター効率の向上で180kmとしました。ミニキャブ・ミーブの航続距離に対して約35%の向上になります。航続距離が増えたことで、充電する頻度が少なくて済みますし、また、地方ではガソリンスタンドが近くにない所も多いので、使い勝手も良くなります。
とはいえ、正直まだまだ改善したいポイントはあります。要望はたくさんいただいていますが、それを全て実現できたわけではないです。もっと航続距離が欲しいというお客様もいらっしゃいますし、充電時間をもう少し早くできるようにして欲しいという声もあります。お客様に提供できる価格とのバランスもありますから難しい部分もありますが、できる限り実用性を高めることができたと思っています。
<リチウムエナジージャパン製バッテリーを搭載。容量は先代ミニキャブ・ミーブの16kWhから20kWhに拡大し、航続距離180kmを実現した>

<モーターはインバーターと一体化し、静粛性を向上。最高出力31kW(42ps)、最大トルク195Nmを発揮する>

―― 実際に乗られた方の反応はいかがでしたか?
藤井 試乗会では、従来モデルより使い勝手がかなり向上したということで、非常にポジティブな声をいただいているようです。我々としては、よりお勧めしやすい商品になったのかなと思います。
EVをきちんと整備できるサービス体制が強み
―― 一方、御社は乗用車も含めて10年以上もEV販売を続けてきましたから、販売店もEVを扱い慣れている、というのは軽商用EVを販売する上で大きな強みですね。
藤井 販売店もそうですし、メーカーである我々も様々な実証実験を重ねて、実際の航続距離や使い方のデータも数多く蓄積しています。どんな使い方が一番効果があるのか等、ノウハウを積み重ねてきていますし、実際に使われているお客様の生の声も多く、これは大きな財産になっていると思います。
また、やはり大きいのはサービス面ですね。EVの整備はガソリン車と異なる部分も多いのですが、販売店を対象にEVメンテナンスの資格制度というのを2016年から設けており、EVをきちんと整備できるスタッフを揃えています。そういった経験やノウハウというのは、他社さんよりは一歩先を行っているんじゃないかなと思います。
―― サービス体制が整っていることは、安心ですね。
藤井 そうですね。バッテリーEVもそうですが、乗用車ではPHEVも販売させていただいているので、電動車を扱える人材を育てていかないと、お客様へのサービスを維持していくのが難しくなります。ですので、ここは我々も力を入れています。
特に商用車は、故障してしまうと商売が止まってしまうので、一刻を争う事態になります。すべてのケースに対応できているわけではありませんが、万一の際の対応も、評価をいただけているポイントの一つだと思っています。
―― EVの整備では、どのようなところがポイントになりますか。
藤井 メンテナンスよりも、故障が出たときの診断であったり、駆動用バッテリーの脱着整備、この辺が一番大きなポイントです。特にバッテリー関係を触るとかですね。高電圧ですので、感電しない道具などが必要ですし、知識も必要になります。
EVメンテナンスの資格は、1級から3級まであって、全販社ともいずれかの資格を必ず持ったスタッフが対応しています。入庫いただいた時、資格者にしか触らせません。そのため、資格を持った人間を全販社に配置しているんです。
しかし、これからEV全体の台数が増えてくると、このあたりの体制は、もっと強化していかないといけないと思っています。
ただ、そうなると、おそらくディーラーだけじゃなく、いろんな街のショップさんや、修理工場なんかもEVに対応できる会社がたぶん増えてくるだろうと思います。ですが、自分たちが販売した車は、自分たちできっちりフォローしていくのが基本です。そのための体制は整えていかないといけないと考えています。
他社と切磋琢磨し、EV化を促進していく
―― これまで軽商用EV市場は、国内自動車メーカーでは三菱自動車しか販売していませんでしたが、今後、ホンダやCJPT(トヨタ、ダイハツ、スズキ)も発売を予定しています。軽商用車の中でEVの占める割合が急速に伸びる可能性もあると思いますが、どのように見ていますか?
藤井 あくまで我々の予測ですが、おそらく24年度から25年度にかけて2割ぐらいがEVになり、2030年度に向けて4割ぐらいまで上がっていくんじゃないか、というふうに見ております。ただ、100%まで行くのは、まだまだ遠い話ですね。
―― 一方で、中国製EVを導入するなど、スタートアップ企業も続々と参入しています。
藤井 日本の道路環境、特にラストワンマイルに適した商品性という意味では、まだ我々に分があると思っています。特に走行性能の部分は圧倒的に差があります。ただ、海外のEVメーカーは改良の速度も早いので、この先油断はできません。
一方で、商用車は何かあったときの対応が非常に重要視される世界です。サービス体制や、部品を交換するためのリードタイムなどは、我々の大きなアドバンテージだと思っています。おそらく性能は彼らもどんどん上げてくると思いますけど、我々の強みであるサービスの信頼性はしっかり継続して、安心して使っていただけるようにしていきたい。もちろん、性能の部分も、この先いろいろ考えていきます。
―― 各社のラインアップが出揃うと、軽商用EV市場全体がいよいよ本格的に立ち上がってくると思います。その中で御社は、今後、どのような取り組みを考えていますか。
藤井 他社さんとも共に切磋琢磨しながら、なんとかカーボンニュートラルに貢献していきたいと思います。
活動としては、今までずっと地道に続けてきた活動を継続して、各企業や全国の自治体にアプローチしていきます。EVは、実際に乗ってもらわないと良さを分かっていただけない部分もあるので、試乗会などもやりながら、商品の良さと我々のサービスを含めた信頼性をアピールして、どんどんEVを増やしていきたいですね。
まずは、EVを導入しようと思っていただく人を増やすこと。我々は今まで培ってきた信頼とかノウハウを全面的に打ち出して頑張って販売していきたい。とにかく市場のマインドが「いつかは」ではなく「もう入れよう」というふうになってくれないと難しいですから。そこはウチだけじゃなくて、各社共通ですから、業界全体で盛り上げていきたいと思います。
(取材・執筆 鞍智誉章)
トラック最前線/公道試乗で体感した、いすゞ「エルフミオ」の実力