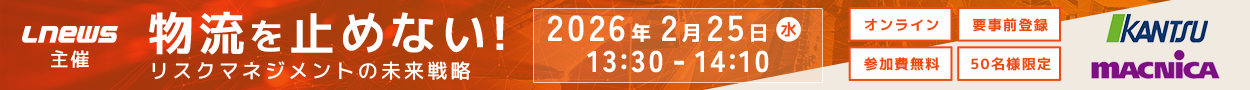ジャパンモビリティショー2025総括/働くクルマにも“水素の時代”が来た!商用車が示した新たな地平
2025年11月14日 16:35 / イベント・セミナー
「ワクワクする未来を、探しに行こう!」をテーマに開催されたジャパンモビリティショー2025。そのコンセプトどおり、今年の会場(各社ブース)には多様なモビリティが集結し、まさに“未来社会の縮図”を感じさせる空間となっていた。
<10月30日~11月9日、東京ビッグサイトで開催されたジャパンモビリティショー2025>

ただ、筆者の目にもっとも強く焼きついたのは、乗用車でも次世代モビリティでもなく「働くクルマの進化」である。特に、大型商用車の領域で“水素”が主役に躍り出たことは、業界全体の潮流を象徴していたように思う。
BEV(バッテリーEV)が環境対応の主流として急速に進化する一方で、長距離・重量物・高稼働を担う大型トラックの分野では、ご存じのように充電時間や積載重量の制約が壁となっている。そうした中で、水素を利用した燃料電池(FC)や水素エンジン採用による環境にも配慮したゼロエミッション化は待ったなし。いよいよ現実的な解として動き出している。
会場を歩きながら感じたのは、「水素社会」という言葉がもはや未来の構想ではなく、物流の現場が取り組む“現在進行形のテーマ”に変わりつつあるということである。(山城利公)
■いすゞ・新型ギガ「GIGA」
安全と信頼を磨き、次の動力へ備える
いすゞは、トヨタ・日野・スズキ・ダイハツと共に進めるCJPT(Commercial Japan Partnership Technologies)連合の一員として、すでに水素トラックの開発を加速させている。小型の「エルフFCV」は2023年から市場導入がはじまり、都市配送や自治体実証で実績を重ねている。
一方、今回のショーでは、前回2023年に展示されていたホンダとの共同開発モデル「GIGA FCV」が姿を見せず、少々残念な印象を受けた。ただし、代わりに展示されていた新型「GIGA」は、同社の未来戦略を感じさせる完成度の高いモデルだった。
<10月30日に発売された、いすゞ新型「GIGA」>

新型GIGAは、ブランドの新たなデザインテーマ「ワールドクロスフロー」を採用。従来の無骨な印象を払拭しつつ、力強さと精悍さを兼ね備えたフロントマスクがとても印象的である。前モデルと並べ比べるとその進化が一目で分かるだろう。実際にドライバー目線で見ても、こうしたデザインの刷新は「次の動力(パワートレイン)への布石」と受け取れる。
安全面の充実も特筆すべきポイント。特に注目したのは、右左折時に歩行者を検知すると自動で作動する「プリクラッシュブレーキ」である。
たとえば左折巻き込み事故を防ぐため、プロドライバーは常に神経を尖らせているが、意外と前方から進入してくる歩行者や自転車の見落としは起こりやすい。実際の乗務でヒヤリとした経験もあり、この機能の有効性は非常に高いと感じた。
さらに「車輪脱落予兆検知システム」を新搭載している。ニュースでもたびたび取り上げられることもあるが、大型トラックの脱輪事故は重大インシデントに直結するだけに、安全への投資として大きな意味を持つ。ただ、会場で説明員にシステム等の詳細を求めたが、「ハブに取り付けられたセンサーを利用して…インストルメントパネル内に警告表示するとともにブザーでも知らせます…」と、いたってカタログ的な説明だけ。もっと具体的に突っ込んだ技術解説を聞きたかったので残念である。
いすゞは水素駆動採用モデルの登場を控え?まず“安全と信頼”の基盤を磨いていることは、商用車メーカーとして極めて現実的かつ戦略的な姿勢といえる。今後、この新型プラットフォームがFCVや水素エンジン仕様のベースになる可能性に期待したい。
■日野「PROFIA Z FCV」
走行実証を経て量産フェーズへ
日野が送り出した「PROFIA Z FCV」は、まさに大型トラックの水素化を実装フェーズに押し上げた一台である。トヨタの燃料電池車「MIRAI」や「SORA(燃料電池バス)」で培ったスタック技術をもとに、日野が大型トラック向けに最適化。2023年5月から数社の大手運送会社での走行実証を開始し、延べ40万km以上を走破した。そしてモビリティショーがはじまる直前の今年10月に、国内初の量産モデルとして正式に市場投入したのは記憶に新しい。
<国内初の量産燃料電池大型トラックとなった日野プロフィア Z FCV>

筆者は実証段階でハンドルを握る機会を得たが、最初に感じたのは“静かさ”と“トルク感”の両立だった。積載状態での発進時の滑らかな立ち上がり、途切れのない加速フィールはまさに電車に乗っているかのよう。大型トラックとは思えないほどスムーズで、乗務中の疲労も大幅に軽減される。
最新の量産仕様では、パワートレイン系の耐久性や信頼性の向上に加え、より広域での稼働を考慮し出力アップを果たしているという。さらにフロント軸重の見直しを行うことで、最大積載量の増加も実現している。これは単に走行性能の向上ではなく、“商用車としての採算性”を追求した結果。さらに燃料電池ユニットの配置バランスや制御ソフトの最適化など、見えない部分での緻密な改良が積み重ねられている。
物流の現場では、どんなにクリーンでも「使える」ことが大前提となる。Z FCVは、CO2ゼロと稼働効率の両立を高次元で成立させつつあり、“実用水素トラック”の時代を切り拓く第一人者といえる存在である。
■三菱ふそう・スーパーグレート「SUPER GREAT H2IC/H2FC」
二つの水素技術で市場をリード?
今年のショーでもっとも強い衝撃を与えたのが、三菱ふそうが世界初公開した2種類の水素駆動トラック「SUPER GREAT H2IC」と「SUPER GREAT H2FC」だろう。
<燃料電池大型トラックH2FC(左)と水素エンジン大型トラックH2IC(右)>

H2ICは圧縮水素を燃料とする水素内燃エンジン車、H2FCは液体水素を利用する燃料電池車。なぜ二つの技術を同時に開発するのか?コストが2倍かかり非効率ではと思われるかもしれない。ただ、その理由は明確だ。市場とインフラの成熟度に応じて、ユーザーが選べる選択肢を早期に提示するためである。
水素エンジンは既存のエンジン技術を活かせるため、開発・導入コストが比較的低く、整備体制の移行も比較的容易。一方で燃料電池は、CO2排出ゼロという究極の環境性能を持ち、長期的な輸送インフラにおいて重要なポジションを担うことになる。
三菱ふそうは、この二正面開発によって短期・中期・長期の3フェーズを同時に押さえる戦略を描いているのだろう。まさに“水素社会への橋渡し役”としての立ち位置といえる。
幸運にも、H2ICの同乗試乗を体験した。発進から定速走行までの挙動は、従来のディーゼル車とほとんど変わらない。社内テストドライバーによれば、現段階ではディーゼル比でややトルクが薄い(パワー感に欠ける?)ものの、改良型エンジン(海外仕様ベース)で補う計画であるという。
H2FCについては法整備や液体水素供給の課題が残るものの、すでに量産を視野に研究が進められている。インフラ整備の進展とともに、公道実証のはじまりが楽しみである。これらの開発に向かう姿勢は、商用車メーカーとしての先見性を強く感じさせる。
水素は「未来の燃料」から「現場の燃料」へ
今回のジャパンモビリティショーを通して感じたのは、水素が“夢のエネルギー”ではなく、“現実の燃料”として動き出していることである。
自動車メーカーだけでなく、ENEOSや岩谷産業などエネルギー各社が、可搬式水素ステーションや自家発型供給装置を積極的に提案している。また今後、物流拠点単位での地産地消的な水素供給網が構築されつつある。これにより、燃料コストや供給リスクが安定すれば、商用車の水素化は一気に普及段階に入るだろう。
実際、運行現場でもっとも重視されるのは“止めない輸送”である。水素トラックなら充填10~15分で再び走り出せ、航続距離も500~800km、液体水素仕様なら1200kmにも達する。この稼働率こそが、物流の生命線となる。今後は、都市圏の短距離配送をBEV、都市間輸送を水素トラックが担う。そんなハイブリッドな使い分けが主流になるだろう。
そして「働くクルマ」が未来を先に走り出す
ジャパンモビリティショー2025は、単なる未来のモビリティ展示会ではなく、「水素社会の実装元年」を象徴する場といっても過言ではないほど興味深かった。とくに商用車分野では、開発・運行・燃料供給・整備インフラが一体となって進化をはじめている。
自動車メーカーにとっても、エネルギー事業者にとっても、そして物流事業者にとっても、水素はもはや“環境対応”の手段ではなく、“ビジネスを止めないための手段”になりつつある。働くクルマの現場が、未来を先に走り出した。それは、理想の技術ではなく、現場のリアルを支える確かな変革の証でもある。
【文:山城利公(やましろ・としまさ)】
1963年・東京生まれ、モータージャーナリスト/プロドライバー
200万km(20年・地球50周以上)におよぶ無事故運行の実績を持ち、商用車技術と物流業界に精通。実体験と現場視点をもとに、クルマ社会の「今」と「未来」を発信している。
大型けん引免許/自動車整備士(国家資格)/整備管理者(選任資格)/国内競技運転者許可証A級(JAF公認)/日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員
三菱ふそう/水素駆動大型トラック開発、全方位で進める
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています