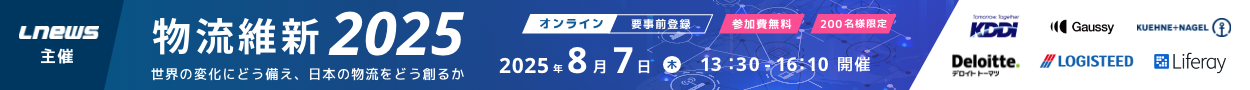トラック最前線/SBフレームワークスに聞く「EVトラックへの期待と課題」
2024年04月17日 09:58 / トラック最前線

環境負荷低減に向け、運送業界でもEV(電気自動車)を導入する企業がこのところ急増している。ソフトバンクグループで物流事業を手がけるSBフレームワークス(東京・江東区)も、昨年12月に三菱ふそう「eCanter」を導入。現在、運行面の検証に取り組んでいる。そこで同社の関根孝将執行役員兼トランスポート事業本部本部長兼統括営業部統括部長に、現在の状況や課題、今後の展望についてお聞きした。(取材日:3月26日)
EVトラック本格導入に向け徹底的に検証
SBフレームワークスは、ソフトバンクグループの一員として3PL事業、輸配送事業、フルフィルメント事業の3つの事業ドメインでサービスを展開している企業。このうち輸配送事業としては、自社保有34台のトラックで、関東圏を中心とした各社物流センターを結ぶ独自輸送網を構築し、大口・小口問わず様々な商品を配送するサービスを提供している。
同社は2023年12月に、同社初のEVトラックとして三菱ふそうの「eCanter」を導入した。東京都が推進する「Clear Skyサポーター」の一員として、大気環境改善に向けた取り組みを継続して行っている同社だが、さらなる改善施策として導入したものだという。
「東京都がCO2削減を推進する取組みとして、貨物運送事業者のエコドライブ等の日常的な努力を実走行燃費で評価する貨物輸送評価制度というものがあるのですが、こちらで6年連続最高賞の三ツ星を受賞するなど、これまでも環境問題に向けた取り組みを積極的に続けてきました。今回のEVトラックの導入は、その取り組みの一環です」と関根氏。社会の要請に応えるために何をすればよいか、エネルギー利用を最適化するマネジメントはどうあるべきか、というところから一つの選択肢としてEVトラックに着目したという。
<SBフレームワークス 執行役員兼トランスポート事業本部本部長兼統括営業部 関根孝将統括部長>

とはいえ、運送事業者のEVトラック導入事例はまだ多くない。特に中小規模の運送事業者での導入例は数えるほどだ。したがってデータもほぼない状況で、たとえ環境には優しくても実際にビジネスとして成立するか、つまり運送トラックとして実用できるかは未知数といえる。さらに、それが同社の運用状況に本当に合致するかはわからない。「運送事業者としての規模からすると、企業イメージの看板として導入するほどの余裕はない。実際に業務に使えなくては困るわけです。そこでまず1台を導入し、検証を始めたところです」。
同社としては、基本的には今後もEVトラックを増車していきたいと考えている。ただ当然ながら、それにはEVトラックが実務をこなせるか、まずはしっかりと見極めることが必要というわけである。そこで半年から1年の期間で検証を重ね、判断していきたいとしている。
予想を上回る電費性能
今回同社が導入したのは、最大積載量3トンの三菱ふそう「eキャンター」で、カタログ値の一充電走行距離は100km。eキャンターは昨春に新型モデルが登場しているが、補助金と納期の関係で従来モデルの導入となった。
<SBフレームワークスが導入した三菱ふそうeキャンター>

運行は、午前中に都内から神奈川方面への定期運行、午後は都内近郊での配送業務を行っている。1日の走行距離は60~70km程度。今のところ、実証ということもあり特別ルートでの運行だという。なお、充電設備は同社の拠点にはなく、三菱ふそうの店舗などルート途中で充電している。またドライバーは、データのバラつきを少なくするため専任としている。
EVトラックを本格的に導入できるか否か、検証すべき項目は多い。大きく分けると航続距離、充電管理、メンテナンス性、ドライバーの負担など多岐に渡る。
実証開始からまだ3ヵ月程度のため、正確な判断はできないというが、まず運行を開始してみて意外だったというのが航続距離、電費性能だ。EVに限らず、トラックでも乗用車でも燃費や電費はカタログ値から乖離することが多い。「eキャンターもカタログ値をかなり下回るものと想像していました。しかし、実際に運行してみるとカタログ値とそれほど差がなかった」と関根氏。もちろん気温や天候、渋滞などの条件で電費は変わってくるが、これまで実証を行った期間がバッテリーには厳しい冬季であったことを考えると、今後も心配は少なそうだ。なお、渋滞の中で暖房を使うと7分間で約1km分の電気を消耗するが、暖房を使わなければカタログ値より電費が10%向上したという。
<eキャンターの運転席。操作はディーゼルトラックと変わらない>

多くの事業者もEVトラックの実力に関心
一方、メリット、デメリットの両方があるというのがドライバーへの負担。ディーゼル車のような振動がないため乗り心地が良く、運転していても疲労が少ないのはEVならではのメリットだ。「乗りやすく、音も静かなので疲れも少ない。将来の人材確保の点でもアピールポイントになるのでは」と関根氏も評価する。
しかし、どうしても走行中にバッテリー残量が気になるのがマイナスポイント。関根氏も「身体的には楽でも、心理的な負担はある」という。バッテリーの残量と充電スポットの場所を気にしながら走行するので、ドライバーとしては神経を使うことは間違いない。走行を重ね、バッテリーの減り方が掴めてくると負担が少なくなるとは思うが、余裕を持たせた運行コースを設定するなどの工夫も求められるところだ。
<eキャンターのドライバーを務める林さん。EVトラックは乗り心地が良いという>

このドライバーの心理的負担にも関連するが、やや厳しい評価といえるのが充電管理についてだ。充電のタイミングや充電器の場所、充電場所で待機が発生するのか、といったデータを蓄積中で、1日の運行を終えてから充電する、または運行途中で充電するといったパターンも繰り返し、実際にどのような使い方が最適なのかを確認しているという。
理論上は、数多く設置されている公共の充電器を活用すれば効率の良い運行が可能なはずだが、実際にはトラックが使える公共充電器は非常に限られており、それを考慮した運行コースにならざるを得ないのが実情という。同社もEVトラックが複数台になれば、拠点に充電器を設置するとしており事情も変わってくるというが、少なくとも公共充電器を主とした運用スタイルは、ルートや走行距離など、トラックの使い方が限定されてしまうのが実情といえるだろう。
ちなみに検証項目のうち、メンテナンス性はまだ3か月という短期間のため、今のところはわからない。現在まで不具合はなく、この検証結果が出るのはもう少し先になりそうだが、乗用EVでもメンテナンスについて大きな問題はないといわれていることからも、EVトラックでも期待しているという。
一方、顧客からの反応は良く「特に外資系の顧客は高く評価してくれる」とのこと。やはりEVトラックは、環境問題への取り組み姿勢をわかりやすく伝えるツールであることは間違いない。
また、納品先で声を掛けられることも多いという。「EVトラックについて、実際の性能など、多くの運送事業者や荷主が気にしているようです」と関根氏。「将来的には導入を考えている。しかし、仕事に使えるかわからないから、導入には躊躇してしまう。EVトラックの実力が知りたいのは皆さん同じなのではないでしょうか」と分析する。EVトラックは未知の存在だけに、不安を感じている事業者が多いということだろう。今後、実際の走行データなどが業界内で広く共有されるようになると不安も解消し、普及に弾みがつく可能性も高い。
<導入したeキャンターは3トン積みのドライバン。積込みや荷卸しも通常のトラックと変わらない>

車両価格と充電インフラが大きな課題
検証開始からまだ間もない同社だが、今のところ大きな問題はなく、良い手応えを感じているという。
とはいえ、今後に向けては課題もある。
まず大きな課題といえるのが、車両価格と補助金だ。普通のディーゼルトラックに対して「補助金なしでは大型車より高く、かなり割高になる」(関根氏)のが実情。そのため補助金の活用が条件となるが、それには納期も問題になってくる。納車時期によっては補助金を得られない場合もあるからだ。実際、同社も補助金申請が通らず、一度EVトラック導入を断念した経緯があるという。
EVトラックの車両価格が大幅に引き下げられれば別だが、現状では補助金無しでは導入は難しい。そのため費用対効果でEVトラックを見た場合、補助金制度の内容によって実用性が大きく左右されることになる。
また、充電インフラ整備も大きな課題だ。トラックでも使える公共充電器が増えれば、運行面での自由度も増し、不安も少なくなる。が、実際のところ、どのように整備されていくのかは不透明だ。政府では充電器を拡充していく方針を掲げているが、数が増えても実際には乗用車しか使えない充電スポットであればあまり意味がない。充電ポイントによって運行の仕方も左右されることになるため、その整備状況はEVトラック導入計画に大きく影響する。
関根氏はさらに、バッテリー交換式EVトラックの実用化なども気になるところだという。インフラの変化によっても車両選択が変わってくるから、これは非常に重要なポイントといえるだろう。またトラックメーカーが今後どのようなEVラインアップ構築を考えているかも情報収集が欠かせない。車両だけでなく運行形態や拠点の整備などにも影響してくるだけに、これからEVトラック導入を進めていく上で、政府の施策やメーカーの方針は重要なところだ。
持続可能な社会への貢献を継続
EVトラックの増車計画に関しては、検証を終えてから結論を出したい、という同社だが「エネルギー利用の最適化を推進して、持続可能な社会に貢献する、というところは、今後も継続していきたい」と関根氏は語る。「EVトラックを実際に検証するという、この一歩を踏み出すか踏み出さないかというところは、今後に向けて非常に重要なポイントになる。あの時やっておいて良かったね、となるようにしっかり検証して、目的に向けて取り組みを進めたい」という。
まだまだ課題の残るEVトラックだが、しかし、それだけに楽しみだと関根氏。「今、いろいろと検証できる立ち位置にいるので、しっかりと、ある意味使い倒す。様々な検証をして、実務運用面もクリアできるような増車の仕方、使い方をぜひ前向きに考えたいですね」。
検証で、EVトラックの特性をしっかりと理解することができれば、本格運用に向けた増車計画も具体化し、同社の環境への取り組みも大きく前進することになる。今後も同社の動向には注目されるところだ。
(取材・執筆 鞍智誉章)
トラック最前線/トラック事業者の心強い味方「トラックGメン」、スタート1年後の成果