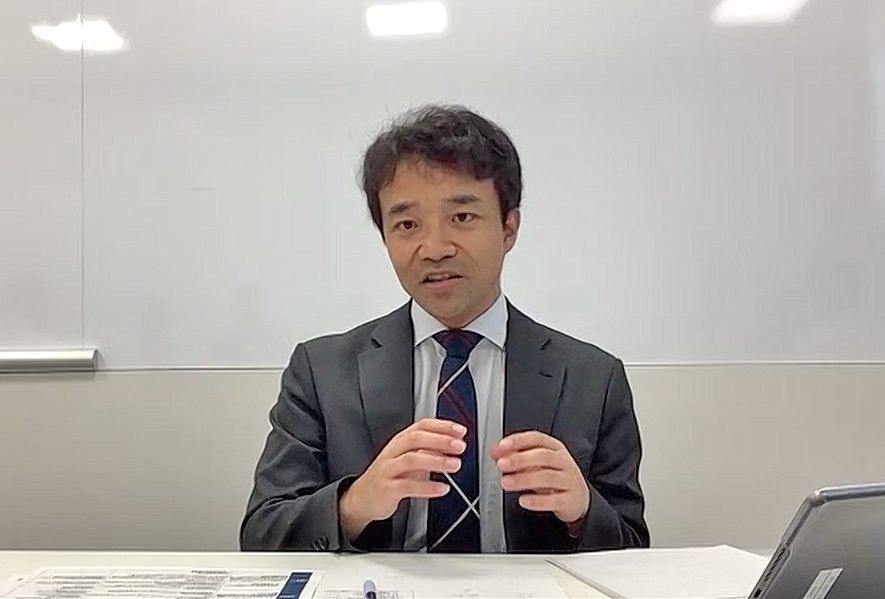日本郵便は7月31日、郵便局で発生した点呼業務不備事案に関し、国土交通省から命じられた「輸送の安全確保命令」に対して、再発防止策等の報告を行った。
点呼の適正実施や飲酒運転の根絶のため、代表取締役社長を中心とした経営層の強いリーダーシップの下、「研修等による意識改革」「職場マネジメント意識の向上や環境整備」「ガバナンス体制の強化」の3本柱の取り組みを推進する。
具体的には、職場マネジメント意識の向上や環境整備では、点呼執行業務に携わる社員等について、早期に貨物軽自動車安全管理者講習の受講と貨物軽自動車安全管理者の選任を進める。年度内に5万人の受講・選任をする計画で、遠隔点呼が必要となる小規郵便局などで優先的に選任を行う計画だ。
また、点呼のデジタル化を推進。全集配郵便局でアルコールチェックや記録の電子化が可能となる点呼関連システムの導入を進め、帳票依存からの脱却を図ることで、より的確な実態確認が行える環境を整備。小規模郵便局では遠隔点呼と業務後自動点呼も導入する。
9月末までに、全集配郵便局にシステム・機器を配備、11月末には、全集配郵便局でデジタル点呼の運用を開始する予定としている。
ガバナンス体制の強化では、一般貨物自動車運送事業許可取消後も引き続き安全統括管理者を社内で選任し、安全対策協議会において、安全管理を実施する。本日付けで、五味儀裕執行役員を新たな安全統括管理者に選任した。また9月を目途に、本社に安全を統括する責任部署を新たに設置する予定だ。
<五味執行役員>
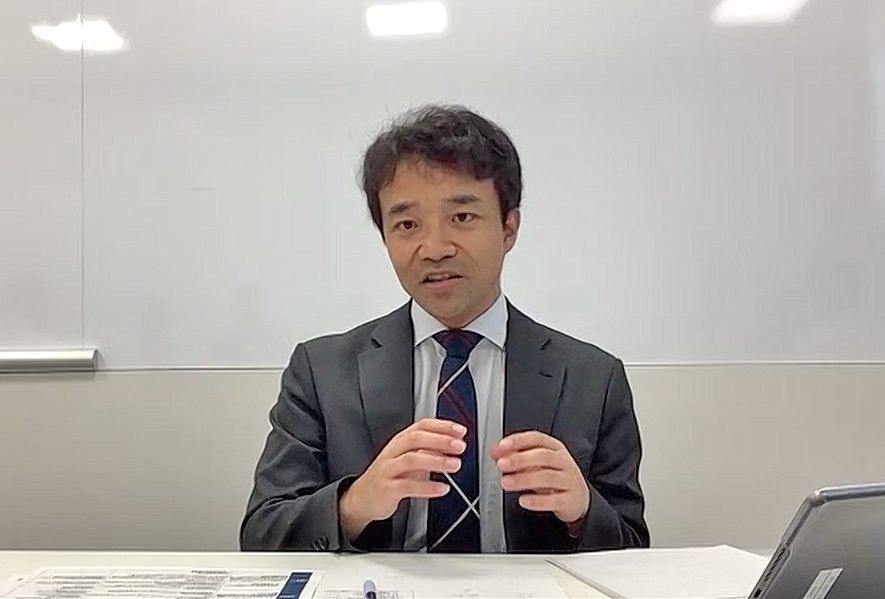
5万人の貨物軽自動車安全管理者について、五味執行役員は、「貨物軽自動車安全管理者は、必要な研修を受講する必要があり、インフラを整えている。そのため、徐々に増えていくのではなく、年度末に向けて増えるイメージだ。ただ、地方部の小規模な郵便局では、対面点呼や立ち合いが1人の配置となったり、また、休日の夜間帯とか遠隔点呼や業務後自動点呼が必要となる。遠隔点呼をするには、点呼実施者は、貨物軽自動車安全管理者でなければならない規定があるので、小規模郵便局を優先して、貨物軽自動車安全管理者を選任する」と述べた。
その上で、「貨物軽自動車安全管理者を選任することで、現場の安全に対する意識改革のツールとしても使っていきたいので、できれば早めに全国の各郵便局に貨物軽自動車安全管理者が1人はいる状態を作って、そこから底上げするイメージを持っている」と語った。
また、安全を統括する責任部署については、「まずは本社で、再発防止策が有効に機能しているのかなどをチェックする安全管理について一元的に責任を負う部署を設置する。まずは、本社で部署を作り、支社でも対応する部署を作る。そこのメンバーが中心となって、5万人の貨物軽自動車安全管理者をしっかりサポートする体制を作る」と説明した。
そのほか、意識改革については、集配関係社員約12万人を対象に、動画視聴・理解度テスト・スモールミーティングの構成を主とした研修を実施。理解度テストは100点を取れるまで実施し、定期的に取り組む。
■日本郵便株式会社による点呼業務の不備事案の再発防止策等の報告
日本郵便/6月に全国13支社中2支社で通勤中の「酒気帯び運転」3件発生
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています